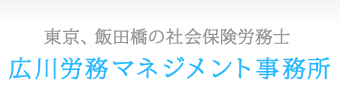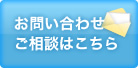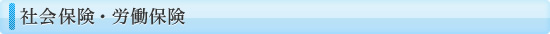
社会保険・労働保険手続代行
- 1.社会保険
- (1)社会保険とは
一般的に社会保険とは、医療保険である健康保険と年金保険である厚生年金保険を総称して社会保険といっています。
健康保険と厚生年金保険は、法律により、株式会社などの法人事業所と原則として5人以上の社員が働いている個人事業所は強制的に加入を義務づけられています。
保険料は会社と従業員の折半負担となっています。
- (2)健康保険
会社員とその扶養家族が病気やけがをしたとき、出産したとき、亡くなったときに必要な保険給付を行う制度です。
健康保険には、健康保険協会が管轄する「協会けんぽ」と健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険」とがあります。
- (3)厚生年金保険
主に、基礎年金である国民年金に上乗せして年金を支給する公的年金制度です。
加入者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い、労働者とその家族の福祉の向上に寄与することを目的にしています。
- (4)どんなときに、どういう手続をおこなうか
- ①会社として新規に加入するとき
→新規適用届
- ②標準報酬月額の見直しを行うとき(年1回 7月)
→被保険者報酬月額算定基礎届
- ③従業員を採用したとき
→被保険者資格取得届、扶養異動届、国民年金第3号被保険者資格取得届
- ④従業員が退職したとき
→被保険者資格喪失届
- ⑤従業員の扶養家族に増減が生じたとき
(結婚、出産、死亡、被扶養者の退職・収入の増減など)
→健康保険被扶養者異動届、国民年金第3号被保険者資格取得届
- ⑥従業員の氏名が変更になったとき
→被保険者氏名変更届
- ⑦従業員の住所が変更になったとき
→厚生年金被保険者住所変更届
- ⑧従業員や被扶養者が出産したとき
→出産手当金請求書・出産一時金請求書
- ⑨健康保険証を紛失したとき
→健康保険証再発行申請書
- ⑩従業員が定年になり再雇用するとき
→資格取得・喪失届
- ⑪従業員が病気やけがで会社を休んで、給与が支給されないとき
→傷病手手金請求書
- ⑫昇給または降給があったとき
→被保険者報酬月額変更届
- ⑬賞与を支払ったとき
→被保険者賞与支払届
- ⑭本人または扶養家族が死亡したとき
→埋葬費請求書
- ⑮従業員が70歳になったとき
→厚生年金保険資格喪失届
- ⑯会社の名称や所在地、代表者が変更になったとき
→適用事業所名称・所在地変更届、事業所関係変更届
- など
- 労働保険
- (1)労働保険とは
労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険をまとめた総称です。
労働保険は、法人・個人を問わず、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態にかかわらず、1人でも雇用する事業主は強制的に加入が義務付けられています。
労働保険の適用事業は雇用保険と労災保険の保険料の申告納付を一本化して取り扱う「一元適用事業」と、雇用保険と労災保険の適用の仕方を区分する必要があるため、保険料の申告、納付を別個に行う「二元適用事業」(建設、農林・水産の事業など)に区分されます。
- (2)雇用保険
主に、労働者が失業したときに、再就職するまでの生活の安定を図るための失業給付などを行う制度です。高年齢者の継続雇用や、育児休業した場合の援助のための給付も行います。
また、失業の予防、労働者の能力開発、向上等の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険の保険料は従業員と会社の両者が決められた率の保険料を負担します。
- (3)労災保険
労働者が業務上の理由または通勤途上でのけが、病気に対して治療したり、障害や死亡について労働者やその家族に年金・一時金などの給付を行うことで生活の安定と福祉の向上を目指している制度です。
労働基準法は、労働者が業務上の原因でけがや病気になった場合は、会社に補償を義務付けていますが、この補償が確実になされるように、会社が加入することが義務付けられているのです。
労災保険の保険料は全額会社負担になります。
- (4)労災保険の中小事業主等の特別加入
労災保険は労働者以外の方(代表取締役等)であっても、業務の実態等から加入、適用が認められる制度があります。
この、「中小企業主の特別加入」は、常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売・飲食業は50人以下、卸売・サービス業にあっては100人以内、その他の事業は300人以内の会社の事業主に限られ、労働保険事務組合に事務処理の委託をする必要があります。
- (5)労働保険未加入のリスク
労災保険未加入の場合、事故発生後に加入手続をとることになります。
平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。これにより、事業主が労災保険の加入を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合は、遡って保険料を徴収するほか、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%を徴収されることになります。
- (6)どんなときに、どういう手続をおこなうか
- ①従業員を初めて雇ったとき
→適用事業報告、労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、
雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
- ②年度更新(年1回 7月10日まで)
→労働保険概算確定保険料申告書
- ③従業員が入社したとき
→雇用保険被保険者資格取得届
- ④従業員が退職したとき
→雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書(離職票)
- ⑤従業員の氏名が変更されたとき
→雇用保険被保険者氏名変更届
- ⑥従業員が60歳に達したとき
→60歳到達時賃金証明書、高年齢雇用継続給付支給申請書
- ⑦従業員が業務上または通勤途上でけがをしたとき
→療養補償給付申請書、休業補償給付申請書、障害補償給付支給申請書
- ⑧従業員が育児休業するとき
→育児休業基本給付金支給申請書
- ⑨従業員が介護休業をするとき
→介護休業給付金支給申請書
- ⑩雇用保険証を紛失したとき
→雇用保険被保険者証再交付申請書
- ⑪会社の名称や所在地、代表者が変更されたとき
→労働保険名称・所在地等変更届、雇用保険事業所各種変更届
- など
 ページの先頭へ戻る
ページの先頭へ戻る