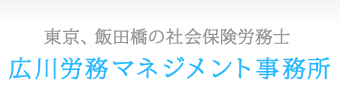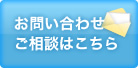賃金制度
- 1.日本の賃金制度の流れ
- 日本の賃金制度について、終戦後から現在までの大まかな流れをみると、次のように区分されると一般的に考えられています。
- (1)終戦後~1960年頃 生活保障中心
生活することを最優先に考えざるを得ない時代。社員の生活安定を図る見地から、年齢別生計費カーブを基準にした賃金体系をとっていた(年齢給が主体)。職務給制度も一部とられていた。 - (2)1960年~1980年頃 年功・学歴基準
徐々に個々の能力に応じた賃金への移行を図ったが、そのノウハウ・制度が確立されておらず、主に学歴・性別・勤続年数を指標にして賃金を決めていた。 - (3)1980年~1990年代前半頃 職能資格制度
高度成長の時代の後半に当たる時期、進学率の高まりや、産業構造の変化などを受けて「能力主義人事制度」として「職能資格制度」といわれる賃金体系が中心になっていった。 - (4)1990年代後半頃~
バブルの崩壊後、低成長時代へ突入し、高齢化による人件費の圧迫が生じてきた。その流れのなかで従来の能力主義人事制度の問題点が大きく表れてきて、脱「職能資格制度」の模索がはじまり、成果主義に代表される新しい賃金制度へ傾斜していった。しかし成果主義も必ずしもうまく機能せず、成果主義と役割主義をを取り入れつつも、模索の状態にあるのが現在。 - 2.各種賃金制度体系の特徴
- 3.制度構築の基本的考え方
- ①社員の不満をなくしていきます。不満は世間的にみて賃金水準が低いという理由よりも、むしろ処遇の仕方に不公平さを感じているケースが多いのです。処遇が能力や成果に基づかず、年功・学歴偏重になっていたり、そもそも「具体的なものさしがない」場合に生じています。
- ②社員にこのように働いてほしいという会社のメッセージ(期待する人材像)を示し、これに向かって努力してもらうようにします。社員にとって、期待される能力、態度行動、成果が知らされ、努力する方向が明確になり、働く意欲が増すことになります。
- ③社員に満足感を与えます。
社員が役割責任を果たし、成果を上げたときは、その事実をきちんと認め、処遇することで、達成感、認定感、成長感という充実が得られるようにします。 - ③固定概念にとらわれず、会社に合った制度を構築していきます。
| 体系 | 基準となるものさし | 特徴 |
|---|---|---|
| 年齢給 | 年齢 | ・年齢とともに上昇する生計費をカバーする意味合いが強い。 ・安定しているが、仕事内容、能力は反映されない。 |
| 勤続給 | 勤続年数 | ・勤続による貢献の意味合い。 |
| 職能給 | 保有能力 | ・職能等級と連動し、インセンチティブの面では優れている。 ・能力の評価に難しさがあり、年功給的な右肩上がりの賃金カーブになりやすい。 |
| 職務給(役割給) | 職務の内容 | ・職務内容、役割により賃金が決まるので合理的ともいえる。 ・仕事内容の変化に柔軟な対応ができにくい。 |
| 成果給(業績給) | 業績への貢献度、成果 | ・個人の業績を競うため、チームワークに問題が出ることがある。 ・間接部門・研究部門の評価がむずかしい。 |
■賃金制度構築の目的、方向性としては、大きくは次のような視点が重要です。
退職金制度
- 1.退職金制度の意義
- (1)長年勤務した社員に対してその功労に報いるため(退職後の生活援助の意味を含めて)
(2)社員の会社への帰属意識を高め、長く勤務してもらうため
(3)優秀な人材を採用するため
(4)退職するときに、スムーズに円満に退職してもらうため - 2.退職金制度の沿革
-
- 昭和27年 退職給与引当金制度創設
- 昭和34年 中小企業退職金共済法制定
- 昭和37年 税制適格退職金制度創設
- 昭和41年 厚生年金基金法制定
- 平成13年 退職給付会計導入
- 平成13年 確定拠出年金法制定
- 平成14年 確定給付年金法制定
- 平成24年 税制適格年金制度廃止
- 3.退職金制度の種類
- (1)基本給連動型
基本給×勤続年数による支給倍数×事由別係数
S字カーブを描く場合が多い - (2)定額方式
勤続年数により一定額を支給
自己都合の減額あり
退職時の評価や役職による加算金を設ける方式もある - (3)別テーブル方式
勤続年数による支給額基準額に退職時の勤続年数別・資格等級別支給率を乗ずる。 - (4)ポイント制退職金
毎年付与されるポイントの積み上げにより支給額を決定する。
資格等級ポイント、勤続ポイント、役職ポイント等 - (5)確定拠出型
- ①中小企業退職金共済制度を利用
基本給、勤続年数、資格等級等により掛金の金額を決定する。
中小企業退職金共済制度は自己都合部分とし、定年の場合の割増率を設ける場合もある。 - ②確定拠出金制度を利用
基本給、勤続年数、資格等級等により掛金の金額を決定する。
- ①中小企業退職金共済制度を利用
- 4.積み立てと給付のしくみ
- 実際の積み立てと給付のやりかたとしては、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度を導入することや生命保険による積み立てる方法などが考えられます。
- 5.退職金制度構築の方向性
-
- ①支給額・水準の決定
- ②資金の積立、支給方法としての制度・枠組み
- ③会計面と税制面
会社の意図する目的に合い、会社の体力に見合った支給水準で、わかりやすく運用しやすい制度を構築することが大切です。
■退職金制度を設ける意義としては次の点が挙げられます。
■制度面での沿革は次のとおりです。
■退職金制度(規程)の種類・方式として次のようなものが挙げられます。
退職金制度構築にあたっては、次の3つの側面からの検討が必要になります。